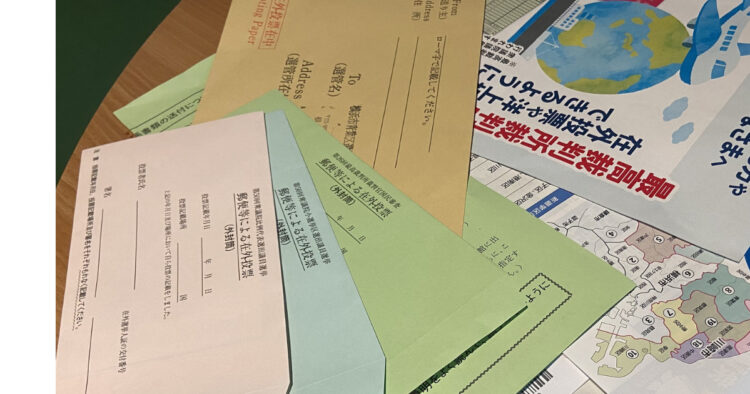「選挙」は健全な民主主義の基本のはずだった。でも、選挙イヤーと言われた今年、世界中で行われた選挙を振り返ると、「選挙」が従来のようには機能しなかった。前提だったはずの良識あるマスメディアは「Old Media」なとど呼ばれ、SNSに乗っ取られたかのようだ。
トランプ再選を目の当たりにしてこう感じた。アメリカだけのことではない。フランスの国民連合も、東京都知事選の石丸信二や、兵庫県知事選の斎藤元彦も、メカニズムは同じだ。政策とか分断とかという次元ではなく、選挙の前提が崩れ、民主主義が壊れている。数秒のショート動画のやけに断言調なメッセージが、何度も何度も再生されて拡散されていくうちに、人々は熱狂し当落を左右してしまう。智恵と時間をかけて私達が少しずつ大切に築いてきた民主主義社会が、せっかちでちゃぶ台返しを楽しむような大衆に壊されていく…。そんな焦燥感に駆られる。



今年2月、「選挙に拠らない」会議体のあり方について知るチャンスがあった。いまさら貴族院とか元老院を復活しようという類の話ではない。選挙だけでなく、「抽選」というのはどうかという大胆な発想だ。これを制度化した先進例が、私が住むベルギーにあるというので、視察にやってきた研究者の徳田太郎氏とともに探ってみることにした。
選挙によらない議会?
そういえば、くじ引きによって選ばれた人々が気候危機やゴミ処分などの生活に密着した社会テーマを話し合う会議のことを、あちこちで聞いたことがあると思い出した。私達は「選挙で選ばれた代議士が立法する」制度しかないと決めてかかっているけれど、「選挙」という方法では、確かに、女性や若者、障害者や教育の低い層など社会的弱者の代表性は担保されにくい。その点、「くじ引き」なら、あらゆる立場を代表するように設計することができる。外交や防衛に関しては無理としても、市民社会に身近なテーマについてなら関心も強く、決定に関与できるなら、多様な人々が参加して活発な議論が可能かもしれない。
だが、ただでさえ仕事と家庭の間にあって忙しい勤め人や学生、老人や若者、介護や育児に追われる人々が、くじ引きに当たったからといって、わざわざ時間やエネルギーをかけて集まってくれるとは私にはとうてい思えなかった。テーマによっては、全くの門外漢で、予備知識も興味もないかもしれない。

でも、すでにベルギーでは、「抽選で選ばれた市民」と、「選挙で選ばれた議員」が、一緒に一つのテーマを議論する熟議体というものが制度になって運営されているというのである。
民主主義の危機は、最近の現象と思われがちだ。だが、専門家によれば、すでにこれまで3つの大波に曝されてきたのだという。19世紀の近代民主主義制度ができてから、最初の波は第一次・第二次大戦のはざまに、二度目の波は冷戦終了頃に。その後、幸いにも専制主義がどんどん民主主義に置き換わっていったというのに、ここ十数年ほどは、民主主義はどんどん後退している(Democratic Backsliding)という。選挙や議会はあるから制度的には民主主義の定義に入りはするが、メディアや司法の独立性が脅かされ、質的に劣化して、機能不全になっている国が急激に増えているのだという。
民主主義の危機は今始まったことではない!
確かに、私自身、ベルリンの壁崩壊直後の90年代には、社会はどんどん市民のために開かれていくような高揚感があった。より直接的な市民参加が奨励されて、パブコメや公聴会、参考人招致、陳情や請願などが活発化したのだという。私自身、欧州議会の「請願委員会」で、小型原子炉開発を欧州の投資優先リストに含めないでほしいと請願したことがあるし、国連に出向いて女性差別撤廃条約委員会に直接陳情を行なったりした。だが、こんなのは「意識高い系」とか「Woke」と呼ばれる一握りの層の活動にすぎないのかもしれない。
近年になって、選挙による議会を補完するために直接市民が関与する例として、陪審員制度、住民投票、抽選による市民議会などがあちこちで試されている。デンマークのコンセンサス会議、フランスや英国などでの気候市民会議は聞いたことがあるが、OECDによれば、様々な試みが世界中でなされてきたのだという。だが、「代議制民主主義」という制度上の足かせのために、市民に決定権は持たせられないことが多かった。
ベルギー人の得意技は、グレーゾーンになんとか落としどころを見出してしまうこと。こうして、「抽選で選ばれた市民による常設の会議体」を成立させたのは2019年。ベルギーの中ではもっとも小さいドイツ語話者自治体(人口78000人)でのことだった。それに続いて、ブリュッセル地域議会(注)と南部ワロン地域議会が、「抽選による市民代表」と「選挙による議員」を混ぜ合わせた常設の会議体を制度化させた。
(注:厳密にいうと、ブリュッセル地域議会の中にも、仏語話者と蘭語話者による個別の会議体があるのだが、ここでは詳細は避ける。)

抽選で選ばれた市民と立法権限を分かち合うという考えに、選挙で選ばれた議員たちが賛同するものだろうか。最初の法案提出から辛抱強く成立までこぎつけた緑の党の女性議員マガリ・プロヴィ氏はこんな風に回想した。「そりゃあ簡単ではなかったわよ。あの頃、議会には、女性や若者の声があまりにも少なかったから。でも2019年の選挙では、気候変動への強い危機感を持った若者が大量に投票して「緑の党」を支持し、抽選で選ばれた市民が加わる熟議体を法制化することに追い風が吹いたのよ。」と。
さて、抽選はどのような仕組みで行われて、どんな人たちがやってくるのか。そして、議論はどのように進行され、最終的に採決されるのか。この制度は、統計学や憲法学、社会学などの専門家が準備した入念なプロセスで実施されている。主にブリュッセルの例で見てみたい。
「くじ引き」はテキトーとは真逆だ
会議の形態は、抽選による市民と選挙による議員が3対1となるように構成される。議員が熟議を支配してしまわないための絶妙なバランスなのだという。一つのテーマについて2カ月ほどの間に約5日間の会議が開催されるのが一つのセッションで、それが年に4~6回行われる。テーマは議員提案もあるが、ネット上の専用プラットフォームを通して市民側から提案することもできる。
National Register(全国個人登録台帳、日本なら戸籍や住民票にあたるものだが、ベルギー人も非ベルギー人も、個人単位で登録されている)を基に、ブリュッセルに住む16歳以上の市民から無作為抽出で1万人を選んで招待状を送付する。応じるかどうかはオンラインか封書で返答するようになっており、応諾した人がプールされ、セッションごとに、人口統計学的な基準に沿って、代表性が担保されるように抽出(層化二段階抽出)するのだという。居住の長短や国籍、教育や言語のレベルなどによる制限はない。

当然ながら勤め人や学生もいれば、小さな子どものいる人、身体の不自由な人もいる。一回の出席に対する報酬はブリュッセルでは約1万円とそれを目的にするには少額だが、小さな子どものいる人には託児所も用意され、ブリュッセルの2つの公用語のどちらかが弱い人には同時通訳も施されるし、勤め人や学生のためには週末開催があったり、社会経験の少ない人には準備セッションも提供されたりと、どんな立場の人でもなんとか出席できるように至れり尽くせりの配慮が施されている。ベルギーでは選挙で投票所を手伝う人なども抽選で選ばれていて、こうした市民サービスへの手当はいわゆるバイトの日当とは比べるタイプのものではないとされている一方、勤務日に当たった場合には、有給休暇が出るような計らいもあるらしい。
一つのテーマについての一連の会議は、よく考えられた構成になっており、「情報提供→熟議→採決」と進む。まず、専門家が議論や判断に必要な情報を提供する。熟議段階では数名の議員と市民の混合グループで入れ替わりながら3~4日かけて議論し、最後には立法上の提案まで作成する。最終日には更にブラッシュアップして採決に持ち込む。議論には熟練したファシリテータが介在し、政治家の意見が強すぎて市民が委縮しないように進めるし、市民の採決は非公開で行われるなど、念入りに工夫されていると感じた。
とはいえ、憲法上のグレーな部分は残ってはいる。ベルギー憲法には「議会は選挙で選ばれた代表で構成される」と明記されているので、市民による採決は「諮問的意味合い」でしかなく、最終的には議員による採決のみが効力を持つことになっている。また、全国個人登録台帳を抽選のベースとして用いることについても、個人情報保護の観点から、相当な議論が尽くされたという。だが、ベルギー市民はこの台帳から個人情報が漏洩することを恐れている風はないし、市民代表が圧倒的多数で支持したものを議員が覆すことは相当に難しく、市民参加の形として社会に定着させることに賛成と見受けた。
それにしても、「ある日突然、あなたは抽選で選ばれました!」という封書が私の元に届いたら、私は真に受けるだろうか。詐欺かフィッシングと恐れて、そのままゴミ箱に捨てないだろうか。
市民に開かれた議会
数名の参加経験者に会えたので尋ねてみると、驚くほど前向きだった。初老のご婦人は、「全然訝しいとは思わなかったわよ。ニュースか何かで聞いていたから。夫やこういうことを良く知ってる友達に聞いてみたら、『面白いじゃないか、行ってごらんよ』と勧められたから」という。大学生の青年は、「授業があって大変だなあと思ったけれど、面白そうだから行ってみようと思ったし、情報セッションも含めていい勉強になった」と答えてくれた。送付した招待状に対する応諾率は約1割(ブリュッセルで2~8%、ワロンでは12%)あるという。もしかして私の予想以上に、ベルギー市民は政府を信頼していて、政治的議論に参加したいと思っているのかもしれないと感じさせられた。

徳田氏は、こういう熟議は「ファシリテータの存在が要」と教えてくれた。確かに、多様な背景の知らない者同士の市民を連れてきて、政治家を混ぜ合わせて「では、議論してください」といっても、そう簡単に活発な議論ができるはずもない。
冒頭で、「選挙」が機能しなくなったことへの危機感に触れた。選挙による代議制を補完するものとして、「抽選」による市民の直接参加に注目し、多くの研究が行われ、地元ベルギーですでに実施されていることも述べた。でも、そんなに悠長なことを言っていられるのだろうか。デジタルやAI時代のスピードはすさまじく、その間にも民主主義は音を立てて崩れているではないか、との焦燥感は強い。
民主主義の危機は選挙のせい? SNSのせい?
ショート動画やXへの投稿で、単純でスカッとするメッセージばかりに繰り返し接し、そのアルゴリズムによってエコーチェンバーに落とし込まれていることにも気づかず、熱狂したり暴徒化したりする大衆の様子は、実に今日的だと思っていた。
だが、ある解説を聞いてはっとした。「群衆は 断言・反復・感染という手法で簡単に扇動できる」―――これは、ヒトラーも愛読したという19世紀の社会心理学者ル・ボンの『群集心理』が説いている。そうか、民主主義は何度も危機にさらされ、その度に大衆は同じような扇動の罠にはまってきたわけで、それはSNSやアルゴリズムがなくても基本は同じだったのではないかと。
世界中で気候危機による大災害や理不尽にしか思えない戦禍が収まる気配を見せない、この年の瀬に問いたい。民主主義の危機をなんとかしなければ地球社会は破滅の道を転げ落ちていく――。しかし、そもそも人々は本当に「秩序」や「安寧」を希求しているのだろうかと。『バベルの塔』が目の前をよぎる。悪貨が良貨を駆逐するさまを見届けたくはない。